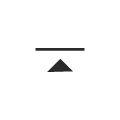2023年度 得度学習会
-
2023年度 得度学習会投稿日:2024年05月08日
2023年度得度学習会が、3月25日(月)~26日(火)教区会館にて開催されました。14歳以上14名、14歳未満8名の方々が参加されました。
日程は、まず、「得度の意義について」の講義を受…
第4期拾学舎(教学・声明作法研修会)開催報告
-
第4期拾学舎(教学・声明作法研修会)開催報告投稿日:2024年05月07日
第4期 第6回(最終回)の拾学舎が、2024年2月17日(土)に開催されました。
2022年12月24日から始まり2年にわたり計6回、「教学」と「声明作法」の学びを深めました。対面開催は第…
【大津別院】同朋の会
-
【大津別院】同朋の会投稿日:2023年04月25日
日時 5月20日(土)午後二時から勤行・法話・座談
場所 大津別院 庫裏仏間
法話 本多 春菜 師(京都教区近江第8組 玄照寺)
先生のお話を受けて、お互いを聞きあう座談の場を大切…
第16期 伝道研修会 開催報告
-
第16期 伝道研修会 開催報告投稿日:2023年04月25日
第16期 第6回(最終回)の伝道研修会が、2023年3月13日(月)、14日(火)の二日間の日程で開催され、9名の受講者が修了されました。 第1回開催がコロナ前の2020年2月で、このときは通常通…
第4期拾学舎(教学・声明作法研修会)開催報告
-
第4期拾学舎(教学・声明作法研修会)開催報告投稿日:2023年01月06日
2022年12月24日(土)に、京都教区会館大講堂にて、第4期 第1回拾学舎が開催されました。 今年度は、全6回を通して「葬儀」をテーマとし、「教学の学び」と「声明作法の学び」の前後編二部に分けて…
2021年度 得度学習会 開催報告
-
2021年度 得度学習会 開催報告投稿日:2022年04月15日
2022年3月29日(火)~30日(水)の二日間にわたり、京都教区会館(京都教務所)にて得度学習会が開催されました。
本学習会は、得度受式者を対象に、毎年開催されています。 27…
春季教師試験検定準備学習会 開催報告
-
春季教師試験検定準備学習会 開催報告投稿日:2022年04月15日
2022年2月26日(土)、27日(日)に春期教師試験検定準備学習会が開催されました。
昨年の夏期準備学習会が新型コロナ感染症拡大のため中止となり、春期は「Zoom開催でも是非実施してほ…
第3期拾学舎(教学・声明作法研修会)開催報告
-
第3期拾学舎(教学・声明作法研修会)開催報告投稿日:2022年04月15日
2022年4月9日に、京都教区会館にて、第三期 第6回拾学舎が開催されました。
全6回のうち、第2回までは対面開催で実施していましたが、新型コロナ感染症の拡大以降はZoom開催となりました…
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2020年01月28日
第16期第1回伝道研修会
1984年から開催されている伝道研修会は、教区教化の主要事業のひとつです。聖教を学び、真宗の教学を研鑽する聞法の場であります。聞く、学ぶ事を通して仏に出遇い、仏との出…
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2019年03月12日
第15期第6回伝道研修会
伝道研修会では、二日間に亘ってご講師の講義を受け、攻究において講義の内容を振り返り教学の確認をして、学びを深めていきます。そして両日共に法話実習と合評があります。 …
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2019年02月16日
第15期第5回伝道研修会
伝道研修会では、二日間に亘ってご講師の講義を受け、攻究において講義の内容を振り返り教学の確認をして、学びを深めていきます。そして両日共に法話実習と合評があります。 …
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2019年01月11日
第2期第5回 拾学舎
親鸞聖人御誕生八百五十年お待ち受け事業として、普段は仕事を持ち、平日に実施される事の多い研修会には参加困難の方を対象に、毎回土曜日に開催しています。
前回から教学…
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2019年01月07日
得度学習会
得度式を受式して大谷派僧侶になるということは、法名をいただいてお釈迦様の仏弟子となり、本願念仏を諦かにされた宗祖親鸞聖人の教えを仰ぎ、称名念仏の中で日々の生活を送ることです…
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2019年01月07日
第15期第4回伝道研修会
第15期の後半の3回が今月末より始まります。現在、日本は少子高齢化、人口減少における過疎問題があり、ますます深刻化している状況にあります。この社会的過…
育成員等研修小委員会
-
育成員等研修小委員会投稿日:2018年12月20日
第2期 第4回拾学舎
親鸞聖人御誕生八百五十年お待ち受け事業として、宗祖の領解を通して真宗大谷派僧侶における「教学」と「声明作法」を学びます。研修会や学習会は平日に開催される事が多く、他に仕…